 |
| さいばいコラム | |
| No.66 第5回魚介類種苗生産シンポジウムに参加しました |
2009.10.23 |
| 能登島栽培漁業センター 友田 努 | |
 2009年9月7日から10日にかけて、ベルギーのゲント市において、 2009年9月7日から10日にかけて、ベルギーのゲント市において、第5回魚介類種苗生産シンポジウム(larvi'2009)が開催されました。 このシンポジウムは約4年に1回開催され(過去には ’91、 ’95、 ’01、’05年に開催)、 最も先進的な研究報告や近年の研究成果について議論する場となっています。 ヨーロッパでは、格式のある会議だそうです。 今回は、世界40カ国から200名以上の研究者が参加しました。 日本からの出席者は大学関係者を含め計14名で、 水研センターでは、栽培漁業センターから宮津の升間場長と私の2名が、 養殖研究所から宇治氏が参加しました。 |
|
| larvi'2009 | |
| シンポジウムは、 1.親魚養成、2.発生生物学、3.栄養学研究、4.形態異常、5.種苗生産技術、6.微生物学と健康管理の 6つの分野に分かれ、それぞれ口頭発表とポスター発表という形で発表の場が設けられています。  口頭発表は本シンポジウムの科学委員会で事前に選ばれた、 口頭発表は本シンポジウムの科学委員会で事前に選ばれた、優れた内容の45課題のみに許可されます。 すり鉢状になっている会議場の壇上に立ち、 パワーポイントを使って英語で発表するスタイルで、 所要時間は質疑応答を含めて20分間です。 ポスター発表は4日間の展示期間中、 来場者に研究成果のポスターを自由に見ていただき、 各ポスターセッションの時間(20〜30分間)に、 座長が優れていると判断したポスターを取り上げて、 会議場で座長から作成者へコメントを求めるというスタイルでした。 一般的なポスター発表は、作成者がポスターの横にずっと張り付いて、 ポスターの内容に興味を持たれた来場者から説明を求められたときに 説明するというスタイルなのですが、 今回のポスターセッションは、それとは異なっておりました。 升間場長は“マグロの親魚養成と種苗生産”について口頭発表、 私は“マダラを健全に育てるエコロジーな方法”についてポスター発表を行いました。 |
|
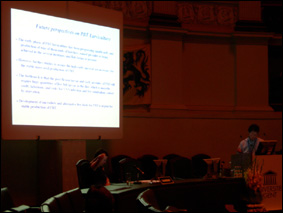 升間場長の発表はシンポジウムの二日目(9月8日)でした。 海外での発表経験が豊富な升間場長は英語も流暢。 マグロの飼育環境等(光条件等)に対して各国視聴者から興味深げな質問が 多々寄せられ、大変好評でした。 発表終了後もスキンヘッドの研究者(一見、スペイン人)が質問に押し掛けて来る程です。 やはり、日本でのマグロ研究は世界的に注目されているのだなあと感じました。 |
|
| 一方、私の参加したポスター発表ですが、今回は全部で110課題のポスター展示がありました。 私の展示ポスターの前で写真撮影をしている研究者(たぶん、ノルウェー人)が数人見受けられ、 ポスターの下に無造作に置いていた配付資料は半分ほど減っていた様子。 しかし、最終日(9月10日)のポスターセッションでは、残念ながら議題に取り上げられることもなく、 無事?(英語で質問されることもなく内心ほっとした)終了しました。 今回のシンポジウムでは、形態異常、遺伝子や酵素活性関連を 研究テーマにした発表が多かったように見受けられました。 基調講演された吉崎准教授や羽賀助教(東京海洋大学)の遺伝子や形態異常発現に関する先進的な研究成果は 欧米人に非常に高く評価されており、同じ日本人ながらレベルの高さを感じました。 そのような中、ある一匹のマダコの生涯を5ヵ月半にわたって観察し続けたイタリアの研究者の発表がありました。 マダコに“Gino”というニックネームまで付けて見守った、 マダコへの愛にあふれた発表には心温まるもの?を感じました。 さすが、情熱の国、イタリアです。 全発表を通して感じたことですが、一番分かりやすい英語は日本人と中国人のもので、 次いで英語を母国語としない研究者(例えば、スペイン語、イタリア語圏)のものでした。 なお、悲しいことにネイティブの英語は速すぎて全く理解できませんでした。 改めて、語学(英会話力)の必要性を痛感しました。 今回のシンポジウムはこれまでで最も日本人の参加が多かったそうです。 言語の壁は大きいですが、ちっぽけでも自分の足跡を残すことが大切で、 このようにして少しでも日本人の底力を示していくべきだと強く感じました。 |
(c) Copyright National Center for Stock Enhancement,Fisheries Research Agency All rights reserved.