
| 研究情報等 | |
| トピックス | |
No.075 サワラの中間育成における適正飼育条件の把握 -飼育水温について- 2005/09/22 |
伯方島栽培漁業センター |
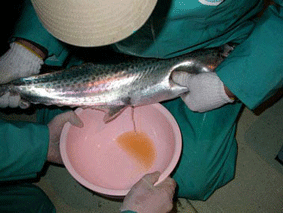 瀬戸内海のサワラの漁獲量は,1986年の6,255トンをピークに減り続け,1998年には約30分の1の196トンにまで激減してしまいました。そこで水産庁では,サワラ瀬戸内海系群を資源回復計画の第1号に指定し,2002年4月より5カ年計画で資源の持続的利用や回復に取り組んでいます。伯方島栽培漁業センターは,資源回復計画の枠組みの中で,瀬戸内海西部海域に放流する健全な人工種苗の生産を担当し,愛媛県・広島県と連携して中間育成の技術開発を行っています。 瀬戸内海のサワラの漁獲量は,1986年の6,255トンをピークに減り続け,1998年には約30分の1の196トンにまで激減してしまいました。そこで水産庁では,サワラ瀬戸内海系群を資源回復計画の第1号に指定し,2002年4月より5カ年計画で資源の持続的利用や回復に取り組んでいます。伯方島栽培漁業センターは,資源回復計画の枠組みの中で,瀬戸内海西部海域に放流する健全な人工種苗の生産を担当し,愛媛県・広島県と連携して中間育成の技術開発を行っています。2002年に瀬戸内海西部海域で愛媛県および広島県が初めて取り組んだ中間育成では,東部海域の岡山県および香川県に比べ,平均日間成長量が3分の2,平均生残率が7分の1と著しく低い結果となりました。これは,同時期の表面水温が,瀬戸内海東部海域で22〜25℃であったのに対し,西部海域では18〜22℃と低かったことが一因ではないかと考え,陸上水槽を使ってサワラ中間育成時の適水温について検討しました。 |
 50kl水槽に平均全長34.7mmの種苗を約2,000尾ずつ収容して,水温19℃区(自然水温),22℃区および25℃区の3試験区を設け,2002年6月9〜29日の20日間飼育しました。
50kl水槽に平均全長34.7mmの種苗を約2,000尾ずつ収容して,水温19℃区(自然水温),22℃区および25℃区の3試験区を設け,2002年6月9〜29日の20日間飼育しました。餌料としては冷凍イカナゴに総合ビタミン剤を展着したものを使用し,毎日6:00〜18:00の間に8〜10回,給餌開始30分程度で飽食量となるよう給餌しました。
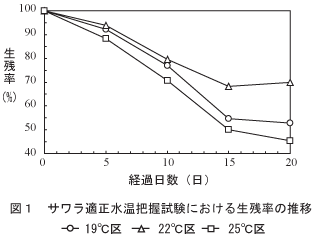 |
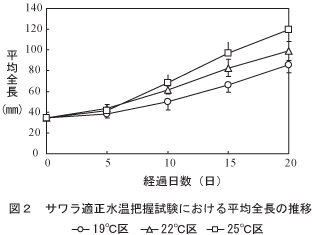 |
一方,最も生残率の高い22℃区では,成長は25℃区にはやや劣ったものの,肝臓中のTG/PL比は安定した増加傾向を示しつつ,試験開始20日目には19℃区と同等かつ最大となり,比較的良好に成長しながら体内にエネルギーを蓄積していたことが示されました。
成長が最も悪かった19℃区では,他区に比べて肝臓中のTG/PL比が高く推移していたことから,摂取したエネルギーは体内に蓄積され,成長に利用される割合は低いものと考えられました。また,19℃区の生残率は22℃区に比べて低く,サワラ種苗の飼育水温としては下限に近いものと考えられました。
したがって,今回の試験で設定した給餌条件(給餌回数8〜10回/日,1回当たり30分の飽食量給餌)では,22℃が適水温であると判断されました。
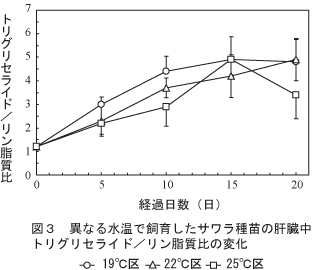 |
 写真3 愛媛県大浜漁協での中間育成
|
サワラの中間育成については飼育方法がまだ確立されておらず,中間育成現場の担当者の判断で実施されているのが現状です。今回の試験結果をふまえ,今後は飼育水温に合わせた適正な給餌管理を実施するとともに,適正な飼育条件を取りまとめて,飼育方法を早急にマニュアル化することが重要と考えられます。
|
|
(c) Copyright National Center for Stock Enhancement,Fisheries Research Agency All rights reserved.